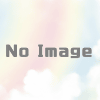アトピー性皮膚炎 加齢 により症状が変化する理由

アトピー性皮膚炎 加齢 により症状が変化する理由を紹介します。アトピー性皮膚炎の症状は、乳児期、小児期、思春期、成人期、そして高齢期と、加齢に伴って変化することが知られています。その背景には、主に以下の複合的な要因が関わっています。
アトピー性皮膚炎 加齢により症状が変化 成長とともに変わる

アトピーとは場所という意味のギリシャ語のトポスに、反対を表わす接頭辞のアをつ
けたもので、「場違いな・奇妙な」という意味をもちます。
成長とともに発症の場所や型を変えながら全身を転々とする(これはアレルギーマーチと呼ばれます) タイプのある種のアレルギー症状に対して、1923年に提唱された概念です。アトピーにおいては、ぜんそくや消化管アレルギーなどもみられますが、最も特徴的なのは、湿疹、かぶれ、かゆみなどの皮膚炎です。
このため、1928年ごろにアトピー性皮膚炎という病名が生まれました。現在ではアトピーといえば、もっぱらこのアトピー性皮膚炎を指すよう
になっています。
アトピー性皮膚炎は、かつては乳幼児の病気と思われていましたが、現在は小・中・高校生、成人にまで広がり、就職や縁談に支障をきたすというような深刻な問題まで引き起こしています。
就職した際にストレスからそれまでアトピーのアの字も知らなかった人が症状に悩まされるケースもあります。
1. 皮膚のバリア機能の変化
- 加齢による低下: 加齢に伴い、皮膚のバリア機能は全体的に低下します。
- 皮脂分泌の減少: 高齢になると皮脂の分泌量が減少し、皮膚が乾燥しやすくなります。皮脂は皮膚表面のバリアの一部を形成しており、その減少はバリア機能の低下に直結します。
- 天然保湿因子(NMF)やセラミドの減少: これらは皮膚の角質層に存在する重要な保湿成分であり、加齢とともにその産生が低下します。これにより、皮膚の水分保持能力が低下し、乾燥がさらに進行します。
- 角質層の構造変化: 加齢により、角質細胞間の結合が弱まったり、ターンオーバーの乱れが生じたりすることで、皮膚の隙間が増え、外部からの刺激物やアレルゲンの侵入を許しやすくなります。
- 乾燥と痒みの悪循環: もともとアトピー性皮膚炎の患者さんは皮膚のバリア機能が低下していますが、加齢による皮膚の乾燥はそれをさらに悪化させます。乾燥が強いと痒みも増し、掻きむしることで皮膚のバリア機能がさらに破壊され、炎症が悪化するという悪循環に陥りやすくなります。
2. 免疫機能の変化(免疫老化)
- 免疫応答の鈍化とバランスの変化: 加齢に伴い、免疫システム全体に変化が生じます(免疫老化)。
- Th1/Th2バランスの変化: アトピー性皮膚炎は、アレルギー反応に関わるTh2細胞の過剰な働きが関与していると考えられています。加齢により、このTh1とTh2のバランスが変化し、アレルギー反応の様式が変わることがあります。一部の患者では、小児期に優位だったTh2優位の炎症が、成人期以降にはTh1優位の炎症に変化することが示唆されており、これが症状の変化に影響を与える可能性があります。
- 炎症性サイトカインの変化: 免疫細胞から放出される炎症を促進する物質(サイトカイン)のパターンが加齢とともに変化することも、症状の現れ方に影響を与えます。
- 免疫監視機能の低下: 高齢になると、体の免疫監視機能が低下し、皮膚に侵入したアレルゲンや細菌に対する反応性が変化することがあります。
3. 皮膚の部位による特徴の変化
- 小児期: 顔面や頭部、体幹、四肢の伸側(肘や膝の外側)などに出やすい傾向があります。
- 成人期以降:
- 苔癬化: 慢性的な掻破(そうは)行為によって皮膚が厚く硬くなる「苔癬化」が顕著になります。特に首周り、顔面、肘や膝の屈曲部、手足の甲などに出やすくなります。
- 顔面・頸部の症状: 顔面や首周りに赤みや乾燥、かゆみが強く出る「顔面型」や、色素沈着を伴うようになることもあります。
- 痒疹(ようしん)の出現: かゆみの強いぶつぶつとした皮疹(痒疹)が体や腕、脚に多発することもあります。
4. 掻破行為の習慣化と慢性化
- 長期間アトピー性皮膚炎を患っている場合、掻破行為が習慣化し、皮膚が慢性的に刺激を受けることで、症状が固定化・難治化しやすくなります。加齢により皮膚の回復力も低下するため、一度掻き壊すと治りにくくなる傾向があります。
5. 合併症や他の病気、薬剤の影響
- 高齢者では、肝臓や腎臓の持病、あるいは服用している薬剤の副作用によってかゆみが強まることがあります。これらの要因が、アトピー性皮膚炎の症状を複雑化させたり、悪化させたりする可能性があります。
症状の変化
- 乳幼児期(生後2二カ月~2歳)…赤い湿潤型湿疹(かきむしると休液がにじみ出る) が顔面や頭部に現われ、やがて全身に広がっていきます。改善しても皮膚にナシの果実の肌のようなプツブツが残ることもあります。
- 小児期(3~12歳)…発疹は乾燥型となりますが、ひじの内側やひぎの裏などにかゆい発疹が現われます。
- 思春期~成人期(12歳~)…かゆみを伴う発疹がときどき繰り返され、やがて皮膚が肥厚して苔癬化していきます。苔癬化とは、皮膚が象のように固くゴワゴワになる状態です。 経過の長いアトピー性皮膚炎の患者さんの皮膚によくみられ、掻破による慢性刺激変化です。
食品、ダニ、ホコリ、花粉、洗剤など原因物質は多数
同じアレルギーである接触性皮膚炎は原因がはっきりしていますが、アトピー性皮膚炎は複雑な因子がからんでおり、以前は原因不明とされていました。
しかし、近年ではアレルゲンになると思われる食品、ダニ、ホコリ、花粉、洗剤などを身の回りから避けることで、かなり症状が改善することが分かりました。つまり、アトピー性皮膚炎の発症の引き金は多数あり、どれが原因かを特定することは困難ではあるものの、引き金となる因子を除去することはかなり有効なわけです。
また、乳幼児の場合は牛乳、卵、大豆による食品アレルギーが目立ちますが、2歳をすぎるとダニアレルギーが多くなることも判明しています。
成人においても、花粉症とも考えられず、食事療法を続けてもなお軽快しないアトピー性皮膚炎の多くはダニが関係しているといわれます。ただ、ダニアレルギーはダニに刺されることによるものではなく(家庭にいるダニのほとんどは人を刺しません)、ダニの糞や死骸の破片がアレルゲンとなることによるものです。
布団などの場合には、ダニ退治に機能を絞った布団乾燥機も多数販売されていますのでおすすめです。
アトピー性皮膚炎の原因となる主なアレルゲン
〔食物〕
牛乳、卵、大豆、魚介類、肉類、米、小麦、ソバなど。各種添加物や残留農薬を含む加工食品。
〔動物〕
犬、猫、ウサギの毛やフケ、小鳥の羽や糞、ダニの糞や死骸の破片。また、ノミとり粉などのペット用薬剤
〔植物〕
スギ、ブタクサ、カモガヤ、ヨモギ、カナムグラ、バラ、イチゴ、マツなどの花粉
〔微生物〕
ブドウ球菌などの細菌類。アスペルギス、アルテリナリア、カンジダなどのカビ類
〔金属〕
ニッケル、クロム、コバルト、水銀、カドミウムなど。また、これらを微量に含む装着用貴金属製品
〔日用品〕
ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(合板、接着剤、新建材、家具など)、染毛剤(ヘアダイ)、ゴム製品、皮膚接触するプラスチック類、化粧品、シャンプー、リンス、セッケン、蚊取り線香、殺虫スプレーなど
〔農薬・医薬品〕
園芸用農薬、自アリ駆除剤、各種医薬品(抗生物質、ピリン剤、サルファ剤、ホルモン剤)